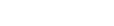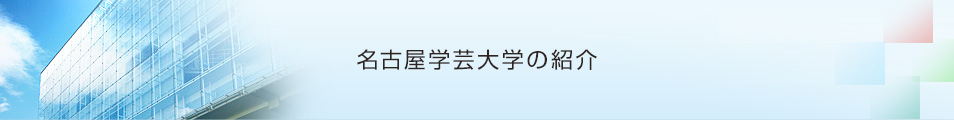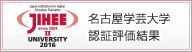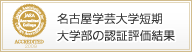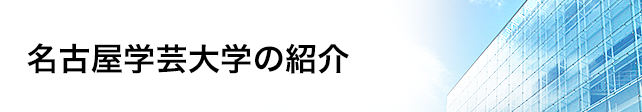
教員組織
教員の教育・研究活動報告
| 所属と職名 | ヒューマンケア学部 准教授 兼 大学院子どもケア研究科 准教授 |
|---|---|
| ふりがな | ふじい まき |
| 教員氏名 | 藤井 真樹 |
| 英語表記 | Maki Fujii |
| 学歴 | 奈良女子大学 文学部 人間行動科学科 卒業(2004年) |
| 京都大学大学院 人間・環境学研究科 共生人間学専攻 修士課程修了(2007年) | |
| 京都大学大学院 人間・環境学研究科 共生人間学専攻 博士後期課程研究指導認定(2013年) | |
| 学位 | 学士(文学)[奈良女子大学](2004年) |
| 修士(人間・環境学)[京都大学](2007年) | |
| 博士(人間・環境学)[京都大学](2017年) | |
| 現在の研究分野 (最大5つまで) |
生涯発達心理学、関係発達理論、質的研究法 |
| 現在の研究テーマ |
|
主な研究業績
| 【著書】 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 題名 | 単・共 の別 |
発行日 | 発行所名 | 備考 |
| カウンセリングと教育相談 | 共 | 2012年7月 | あいり出版 | 15章担当 |
| 保育原理(第5章:発達と保育との関係) | 共 | 2018年3月 | ヴィッセン出版 | 5章担当 |
| 他者と「共にある」とはどういうことか―実感としての「つながり」 | 単 | 2019年9月 | ミネルヴァ書房 | |
| 【学術論文】 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 題名 | 単・共 の別 |
発行又は発表日 | 発行雑誌又は発 行学会等の名称 |
備考 |
| 他者を主体として受け止める -「共にそこにある」こととして- |
単 | 2007年1月19日 | 京都大学大学院人間・環境学研究科平成18年度修士論文 | |
| 方法としての間主観性 -子どもの体験世界へ接近するために- |
単 | 2008年3月1日 | 名古屋学芸大学 ヒューマンケア学部紀要 |
査読有 |
| 関与の「質」、記述の「質」、理論の「質」を問う-事象のアクチュアリティに迫る質的研究を目指して- | 共 | 2009年3月31日 | 京都大学グローバルCOEプログラム研究開発コロキアム成果報告書 | |
| 関係発達研究にかかる「間主観性」概念の現状と可能性‐子どもの自己形成過程における意味に着目して‐ | 共 | 2010年.3月31日 | 京都大学グローバルCOEプログラム研究開発コロキアム成果報告書 | |
| 保育の場における関与観察者の存在の意味を探る:ある園児に投げかけられた言葉をめぐる考察から | 単 | 2010年12月25日 | 保育学研究48(2) | 査読有 |
| 生活世界における「発達」概念の現象学的考察とその再構築に関する萌芽的研究 | 共 | 2011年3月31日 | 京都大学グローバルCOEプログラム研究開発コロキアム成果報告書 | |
| 子どもの「生きられる世界」に導かれるなかで | 単 | 2011年4月25日 | ミネルヴァ書房 学術雑誌 「発達」126 |
|
| 「生きられる経験」から子どもの心の育ちを探る-「発達」の意味を問い直すための予備的考察として | 単 | 2011年12月 | 家庭教育研究奨励金研究報告家庭教育研究所紀要第33号 | 査読有 |
| 共感を支える「共にある」という地平 | 単 | 2012年3月20日 | 質的心理学研究第11号 | 査読有 |
| 子どもの体験としての「遊び」を探る | 単 | 2012年10月25日 | ミネルヴァ書房 学術雑誌 「発達」132 | |
書評 中田基昭 著『子どもから学ぶ教育学‐乳幼児の豊かな感受性をめぐって‐』(東京大学出版会,2013) |
単 | 2014年3月31日 | 人間性心理学研究 第31巻第2号 |
|
| 実感としての他者との「つながり」 | 単 | 2017年1月23日 | 京都大学博士学位論文 | |
| 主題と変奏―臨床便り 第41回 人の生に寄り添う |
単 | 2020年1月 | 臨床心理学 | |
| Exploring the Relationship Between an ECEC Teacher and Children from the Perspective of E-Series time : focusing on the “Slide and Mud Play” | 共 | 2021年5月 | ASIA-PACIFIC JOURNAL OF RESEARCH IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION Vol.15,No.2,pp.111-133 | 査読有 |
| Exploring the Narrative of an Early Childhood Education and Care Teacher from the Perspective of Polyphonic Time | 共 | 2021年10月 | Japanese Psychological Research | 査読有 |
| 他者と「共にある」ために | 単 | 2022年6月 | 金子書房「note」 | |
| つながりの再構築に向けて―Re:リ・コロン再論 第13号特集 つながりの実感 |
共 | 2022年10月 | 質的心理学フォーラム第13号 | |
| 沈黙の共有というコミュニケーション:幼児期における身体に基づくコミュニケーションの重要性 | 単 | 2023年10月 | 質的心理学フォーラム第14号 | 査読有 |
| 人と人との関係性を音楽的に捉えるために:「転調」概念の理論的基盤 | 共 | 2024年1月 | 同志社女子大学学術研究年報 | 査読有 |
| 【学会発表等】 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 題名 | 単・共 の別 |
発行又は発表日 | 発行学会等の 名称 |
備考 |
| 「受け止める―受け止められる」ことの実相-間主観的につかむ(ポスター発表) | 単 | 2007年3月 | 日本発達心理学会 第18回大会 |
|
| 間主観性を支える間身体性(ポスター発表) | 単 | 2007年7月 | 日本認知運動療法研究会 第8回大会 |
|
| 他者と「共にある」こととは(口頭発表) | 単 | 2007年11月 | 日本人間性心理学会 第26回大会 |
|
| 現象学的立場における「発達」のかたち メルロ=ポンティの「身体図式」の観点から (ポスター口頭発表) |
単 | 2008年8月 | 日本人間性心理学会 第27回大会 |
|
| 保育・教育実践に貢献しうる研究アプローチの構築―人の生きる場の「あるがまま」に迫る方法論とは―(ポスター発表) | 共 | 2008年9月 | 日本心理学会 第72回大会 |
|
| 子どもの発話から気づかされる〈語る主体〉としての在り様 -子どものことばから育ちを捉える観点を探る-(ポスター発表) |
単 | 2009年3月 | 日本発達心理学会 第20回大会 |
|
| 人が生きる現場に研究者が参入することへの一考察―参入される側の体験の意味を探る(口頭発表) | 単 | 2009年8月 | 日本人間性心理学会 第28回大会 |
|
| 他者を「わかる」ということの意味を問う:「実践研究」がアクチュアリティをもつとき(自主シンポジウム) | 単 | 2010年3月 | 日本発達心理学会 第21回大会 |
企画者 話題提供者 |
| 子どもが「育つ」ということ:実践の場の「実感としての育ち」からの再考(自主シンポジウム) | 単 | 2011年3月 | 日本発達心理学会 第22回大会 |
企画者 話題提供者 |
| 「自己」の成り立ちにおける「他者」の意味:子どもが「育つ」場の関与・観察から(自主シンポジウム) | 単 | 2012年3月 | 日本発達心理学会 第23回大会 |
企画者 話題提供者 |
| テレビアニメの世界における「祖父母性」(ポスター発表) | 共 | 2012年5月 | 日本保育学会 第65回大会 |
|
| 子どもの体験世界のあるがままに迫ること(自主シンポジウム) | 単 | 2012年5月 | 日本保育学会 第65回大会 |
企画者 話題提供者 |
| 人間科学の方法としての現象学(自主シンポジウム) | 単 | 2012年9月 | 日本人間性心理学会 第31回大会 | 話題提供者 |
| テレビアニメの世界における「祖父母性」(ポスター発表)第2報 | 共 | 2013年5月 | 日本保育学会 第66回大会 | |
| 保育研究における現象学的態度とその記述の意義(口頭発表) | 単 | 2013年5月 | 日本保育学会 第66回大会 | |
| 「つながり」としての他者理解を考える:表象としての「何か」をわかることを超えて(ポスター発表) | 単 | 2013年8月 | 日本質的心理学会 第10回大会 | |
| 「他者理解」の多層性について | 単 | 2019年3月 | 東京フィールド研究会第18回 | |
| 子育てにおける子ども理解を探る:母親のあり方から見る「家庭における育ち」の可能性 | 単 | 2019年3月 | 日本発達心理学会 第30回大会 | |
| 大学生にとっての「一人でいること」の意味について:人間関係の「希薄化」についての探索的検討 | 単 | 2019年9月 | 日本質的心理学会 第16回大会 |
|
| 保育者が実感する遊びの成立に関する研究(1):A保育園の築山遊びから | 共 | 2020年3月 | 日本発達心理学会 第31回大会 |
|
| 保育者が実感する遊びの成立に関する研究(2):A保育園の築山遊びから | 共 | 2020年3月 | 日本発達心理学会 第31回大会 |
|
| 「子育て」と保育の相違から探る「育てる」営み | 共 | 2020年5月 | 日本保育学会 第73回大会 |
|
| 関係性の「変わり目」を音楽的に捉える試み:「転調」理論の射程 | 共 | 2023年3月 | 日本発達心理学会 第33回大会 |
|
| 語り合いから探る子育て中の母親の「変わり目」:「変わる」ことをめぐる体験とは | 共 | 2023年11月 | 日本質的心理学会 第20回大会 |
|
| 保育実践を質的にとらえることで開かれる地平 | 共 | 2023年12月 | 日本乳幼児教育学会 第33回大会 |
|
主な教育上の業績
| 【大学教育の改善に関する活動】 | |||
|---|---|---|---|
| 活動事項 | 単・共の別 | 年月 | 備考 |
| 学生自身が前年度履修した学外実習での体験を記述し振り返る機会を盛り込み、学生自身の子どもとの関わりの体験を基に講義を展開することによって、学生の理論への理解を促すよう工夫した。 | 単 | 2017年4月~現在 | |
| 講義内容の重要事項をまとめたプリントを毎時間配布したり、講義への質問や感想を記述する時間を設け、次回講義時に回答し、学生の理解を促すよう工夫した。 | 単 | 2013年4月~現在 | |
| 高学年の「知識及び技能」と「思考力・判断力・表現力等」に該当する科目について、それまでに習得した知識や技能をもとに適切に「考え、判断し、表現」する力を養うことを目的に、インタラクティブな授業となるよう新しいツールを用いて授業を試みている。 | 単 | 2023年4月~現在 | |
主な職務上の業績
| 【資格・免許】 | |||
|---|---|---|---|
| 資格・免許の名称 | 取得年月 | 発行者・登録番号 | 備考 |
| 公認心理師 | 2022年9月14日 | 登録番号57514号 | |
| 【社会的活動等】 | |||
|---|---|---|---|
| 活動事項 | 期間(年月) | 活動機関 | 備考 |
| 社会福祉法人太陽の家 やまさと保育園 評議員 | 2017年4月~ | ||
| 刈谷市立朝日小学校研修会 講師 「アタッチメントの重要性とそれに基づく心の育ち」 |
2019年8月5日 | 刈谷市立朝日小学校 | |
| 親力アップセミナー「イヤイヤ期の子どもの心の育ちと親のあり方」 | 2023年12月5日 | 名古屋学芸大学ヒューマンケア学部付属子どもケアセンター | |
所属学会
| 【所属学会名称】 | |
|---|---|
| 学会名称 | 日本発達心理学会、日本質的心理学会、日本保育学会、日本乳幼児教育学会 |
| 【所属学会役員歴等】 | ||
|---|---|---|
| 学会及び役員名 | 年月期間(年月) | 備考 |
| 日本質的心理学会 編集委員会 編集監事 | 2014年4月~2017年3月 | |
| 日本発達心理学会国内研究交流委員 | 2015年1月~2016年1月 | |
| 日本質的心理学フォーラム編集委員 | 2019年4月~2022.9 | |
| 国際幼児教育学会 機関誌編集委員会委員 | 2020年1月1日~現在 | |
| 日本質的心理学会査読委員 | 2023年4月~2024年3月 | |
| 日本質的心理学会編集委員 | 2024年4月~現在 | |
主な職歴
| 事項 | 期間(年月) | 備考 |
|---|---|---|
| 名古屋学芸大学 ヒューマンケア学部 助手 | 2007年4月~2012年3月 | |
| 名古屋学芸大学 ヒューマンケア学部 助教 | 2012年4月~2016年3月 | |
| 名古屋学芸大学 ヒューマンケア学部 講師 | 2016年4月~2024年3月 | |
| 名古屋市立大学 人文社会学部 非常勤講師 | 2022年9月~現在に至る | |
| 名古屋学芸大学 ヒューマンケア学部 准教授 | 2024年4月~現在に至る |
受賞学術賞
| 受賞事項 | 年月期間(年月) | 備考 |
|---|---|---|
| 2013年度日本質的心理学会 学会賞 | 2013年8月 |
科学研究費等外部資金導入実績
| 名称 | 題名 | 年月 | 機関名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 大学院生人材育成経費 研究開発コロキアム(京都大学グローバルCOE) |
関与の「質」、記述の「質」、理論の「質」を問う-事象のアクチュアリティに迫る質的研究を目指して- | 2008年4月 | 京都大学 | 研究分担者 |
| 大学院生人材育成経費 研究開発コロキアム(京都大学グローバルCOE) |
関係発達研究にかかる「間主観性」概念の現状と可能性-子どもの自己形成過程における意味に着目して- | 2009年4月 | 京都大学 | 研究代表者 |
大学院人材育成経費 研究開発コロキアム(京都大学グローバルCOE) |
生活世界における「発達」概念の現象学的考察とその再構築に関する萌芽的研究 | 2010年7月 | 京都大学 | 研究代表者 |
| 家庭教育研究奨励金 | 幼児における他者と「共にある」ことの発達的意味-身体的他者関係に着目して | 2010年7月 | 財団法人小平記念日立教育振興財団 | 個人研究 |
主な担当科目と授業の改善と工夫
| 【担当科目名(対象学部・学科)】 |
|---|
| 子ども人間関係(保育科指導法Ⅶ)、幼児理解、生涯発達心理学Ⅰ、子ども家庭支援の心理学、ゼミナールⅠ(研究導入)、ゼミナールⅡ(研究展開)、ゼミナールⅢ(卒業研究)、発達心理学特論(大学院)、発達心理学演習(大学院)、保育内容研究演習(大学院) |
| 【授業の改善と工夫】 |
|---|
| 「幼児理解」では、初めての学外実習へ向かう準備も意識しながら、子どもの発達に沿った理解と援助のあり方をさまざまな具体的事例を通して理解を促す授業を心がけている。「子ども人間関係」では、人間の原初となる乳児期から幼児期にかけて、子どもたちが周囲の他者とどのような人間関係を営み、自らの世界を形成していくのかについて、実際の保育園の映像視聴を重ねながら理解を図るようにしている。「生涯発達心理学Ⅰ」では、「育てられる者」が「育てる者」になるという、人が生涯にわたって発達するあり様を自分事として考えられるよう、受講者の実感を意識しながら事例を通じて授業を行っている。「子ども家庭支援」の心理学では、子どもを育てる家庭の実情や現在の子育て環境を学ぶことを軸として、保育者としていかなる家庭支援が可能であるか、自ら考えられるようになることを目指し授業を行っている。 |