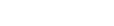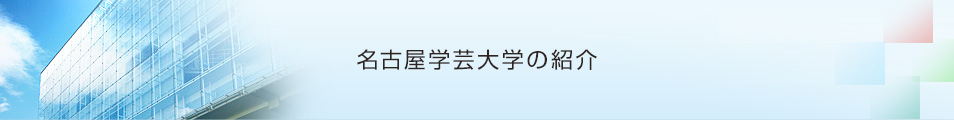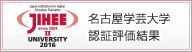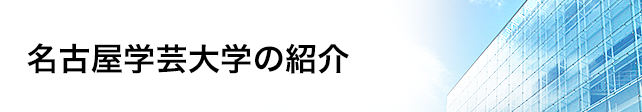
教員組織
教員の教育・研究活動報告
| 所属と職名 | ヒューマンケア学部 子どもケア学科 教授 |
|---|---|
| ふりがな | そうずし のぶこ |
| 教員氏名 | 想厨子 伸子 |
| 英語表記 | Nobuko Sozushi |
| 学歴 | 岐阜大学 教育学部 教育学科 教育学コース 卒業(1976年) |
| 愛知教育大学大学院 教育学研究科 発達教育科学専攻 修士課程修了(2012年) | |
| 学位 | 教育学士[岐阜大学](1976年) |
| 修士(教育学)[愛知教育大学](2012年) | |
| 現在の研究分野 (最大5つまで) |
教育学 、子ども学 |
| 現在の研究テーマ |
|
主な研究業績
| 【著書】 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 題名 | 単・共 の別 |
発行日 | 発行所名 | 備考 |
| 気になる子どもと親への保育支援-発達障害児に寄り添い、心をかよわせて- | 共 | 2011年9月 | 福村出版 | |
| 子どもの育ちとケアを考える | 共 | 2019年4月 | 学文社 | |
| 【学術論文】 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 題名 | 単・共 の別 |
発行又は発表日 | 発行雑誌又は発 行学会等の名称 |
備考 |
| 「幼児期の運動遊びと自信の形成」-竹馬活動の取り組みを通して-(修士論文) | 単 | 2012年3月 | 愛知教育大学大学院修士論文 | 査読有 |
| 「小学生の記憶に残る幼児期の活動や遊び」-卒園児・保護者の調査から-(愛知教育大学 幼児教育研究第16号) | 単 | 2012年7月 | 愛知教育大学幼児教育講座 紀要 | 査読無 |
| 「竹馬活動における運動嫌いの幼児の変化」 (愛知教育大学 幼児教育研究第17号) | 単 | 2013年7月 | 愛知教育大学幼児教育講座座紀要 | 査読無 |
| 幼児の体力・運動能力に関する一考察 | 共 | 2013年12月 | 至学館大学 健康科学研究所年報 | 査読無 |
| 「自然環境における幼児との触れ合い活動によるアクティブラーニングの試み」 | 共 | 2017年3月 | 名古屋学芸大学ヒューマンケア学部紀要第10号・研究ノート | 査読あり |
| 幼児クラスにおける保育者の運動場面での援助・指導の傾向 | 共 | 2018年3月 | 椙山女学園大学教育学部紀要 | 査読あり |
| 保育者・教員養成機関大学における地域発信としての「みどりのこども会」の実践と考察 -ESDをテーマにした幼児向けイベント事業の展開をとおして- | 共 | 2018年3月 | 名古屋学芸大学ヒューマンケア学部紀要第11号・研究ノート | 査読あり |
| 幼児期の協同的な学びを考える―保育者の関わりに視点をおいてー | 共 | 2020年2月 | 名古屋学芸大学資質能力を育てる教職カリキュラム研究 第2集 | 査読なし |
| 【学会発表等】 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 題名 | 単・共 の別 |
発行又は発表日 | 発行学会等の 名称 |
備考 |
| 5歳児における竹馬活動の意義(ポスタ-発表) | 単 | 2011年5月 | 日本保育学会 | |
| 「小学生の記憶に残る幼児期の活動」-卒園児・保護者の調査より-(ポスタ-発表) | 単 | 2012年5月 | 日本保育学会 | |
| 保護者の願いに沿った幼小連携-園児の親の意識調査から-(ポスタ-発表) | 単 | 2013年5月 | 日本保育学会 | |
| 保護者の願いに沿った幼小連携(2) ‐園児の親の追跡調査から‐(ポスター発表) | 共 | 2014年5月 | 日本保育学会 | |
| 保育実践力の育成・向上に関する研究(6) ‐運動場面での言葉掛け‐(ポスター発表) | 共 | 2014年5月 | 日本保育学会 | |
保護者の願いに沿った幼小連携(3) -不登校であった一年生の事例より- (ポスター発表) |
共 | 2015年5月 | 日本保育学会 | |
保育実践力の育成・向上に関する研究(7) -保育職継続に関する要因-(ポスター発表) |
共 | 2015年5月 | 日本保育学会 | |
自然体験が幼児に与える影響について ‐地引網体験を通して‐ (ポスター発表・抄録) |
共 | 2016年5月 | 日本保育学会 | |
幼大・地域・おもちゃプロジェクトの連携による「森の子ども園」の実践 ‐自然の中での遊び・学び・育み‐ (自主シンポジウム・抄録) |
共 | 2016年5月 | 日本保育学会 | |
幼大・地域・おもちゃプロジェクトの連携による「森の子ども園」の実践 Ⅱ |
共 | 2017年5月 | 日本保育学会 | |
4歳児の合宿保育における親の気持ちの変化 (ポスター発表)抄録作成 |
共 | 2017年5月 | 日本保育学会 | |
| 幼児向けESD教育を目指す「みどりの子ども会」事業の実践 (自主シンポ)抄録作成 |
共 | 2018年5月 | 日本保育学会 | |
| 5歳児の園外保育における協同的な学び | 共 | 2018年5月 | 日本保育学会 | |
| 協同的な学びを考える ― 子どもたちが創る「あきまつり」ー |
共 | 2019年5月 | 日本保育学会 | |
| 授業外の大学生活環境を学びに活かす ―学内施設「子どもケアセンター」との協働―(口頭発表) |
共 | 2020年3月 | 日本保育者養成教育学会 | |
| 卒園を前にした5歳児の協同的学び
(ポスター発表) |
共 | 2020年5月 | 日本保育学会 | |
| コロナ禍における保護者との連携
―心の安定を大切にした関わり― |
共 | 2021年5月 | 日本保育学会 | |
主な教育上の業績
| 【大学教育の改善に関する活動】 | |||
|---|---|---|---|
| 活動事項 | 単・共 の別 |
年月 | 備考 |
| 自然環境における幼児とのふれあい活動を通したアクティブラーニング及び地域発信としての「みどりのこども会」の実践」 | 共 | 2015年~2017年 | |
| 【作成した教科書】 | |||
|---|---|---|---|
| 教科書名(対象講義名) | 単・共 の別 |
年月 | 備考 |
| 気になる子どもと親への保育支援-発達障害児に寄り添い、心をかよわせて- | 共 | 2011年9月 | 福村出版 |
| 「子どもの遊びとリズム」教材集 | 単 | 2016年3月 | |
主な職務上の業績
| 【資格・免許】 | |||
|---|---|---|---|
| 資格・免許の名称 | 取得年月 | 発行者・登録番号 | 備考 |
| 幼稚園教諭二級免許状 | 1976年3月 | 岐阜県教育委員会 第1517号 |
|
| 小学校教諭一級免許状 | 1976年3月 | 岐阜県教育委員会 第406号 |
|
| 中学校教諭一級免許状(社会) |
1976年4月 | 岐阜県教育委員会 第18号 |
|
| 高等学校教諭二級免許状(社会) | 1976年4月 | 岐阜県教育委員会 第6号 |
|
| 養護学校教諭二級免許状 | 1976年4月 | 岐阜県教育委員会 第3号 |
|
| 幼稚園教諭一種免許状 | 1994年6月 | 愛知県教育委員会 第10号 |
|
| 幼稚園教諭専修免許状 | 2012年4月 | 愛知県教育委員会 第2号 |
|
| 【社会的活動等】 | |||
|---|---|---|---|
| 活動事項 | 年月 | 活動機関 | 備考 |
| 障害幼児研究会での発表 「自閉症H君の記録-ぼく、お友達ができたよ」 |
2012年3月 | 愛知教育大学幼児教育講座 障害幼児研究会 | |
高校生対象の模擬授業 (資料作成) |
2013年11月 | 愛知県立長久手高校 | |
恵那市教育委員会主催 恵那市立子ども園公開保育及び研究会の指導 |
2016年5月~9月 |
恵那市立二葉子ども園 恵那市立岩村子ども園 恵那市立吉田子ども園 恵那市立やまびこ子ども園 恵那市立みさと子ども園 恵那市立中野方子ども園 |
|
至学館大学附属幼稚園子育て講座 PTA講演会講師(資料作成) |
2016年7月 | 至学館大学附属幼稚園 | |
| 名古屋学芸大学ヒューマンケア学部子どもケアセンター親力アップセミナー講師 | 2017年11月 | 名古屋学芸大学ヒューマンケア学部子どもケアセンター | |
| 至学館大学附属幼稚園教員研修講師 (質の高い幼児教育目指して)(資料作成) |
2018年1月 | 至学館大学附属幼稚園 | |
| 恵那市教育研究会講師 (幼保連携型認定こども園教育・保育要領改訂を受けて)(資料作成) |
2018年2月 | 恵那市教育委員会 | |
| 就園前の子どもがいるママのための地域情報誌teniteo(テニテオ)4~5月号 「しつけのコツ」執筆 | 2018年4月・5月 | 株式会社teniteo | |
| 至学館大学附属幼稚園教育実践発表会 「子どもたちを本気にさせる教育実践」助言者 | 2018年11月 | 至学館大学附属幼稚園 | |
| 清須市保育者研修会 講師 「遊びを通して育つ子どもの力」 | 2018年12月 | 愛知県清須市役所 | |
| 日本保育学会自主シンポジウム 司会 ―幼児期におけるESD事業の展開― | 2019年5月 | 日本保育学会 | |
| 日進市子育て支援者講座 講師 | 2022年5月 | にっしん子育て支援総合センター | |
| 令和5年度育児講座 講座 講師 | 2023年12月 | 瀬戸市せとっ子ファミリー交流館 | |
所属学会
| 【所属学会名称】 | |
|---|---|
| 学会名称 | 日本保育学会、乳幼児教育学会、日本子ども社会学会、 OMEP日本委員会、日本こども学会、日本保育者養成教育学会 |
主な職歴
| 事項 | 期間(年月) | 備考 |
|---|---|---|
| 岐阜市立小学校講師(鶉小学校・方県小学校・黒野学校) | 1976年4月~ 1978年3月(2年) |
|
| 学校法人いずみ幼稚園教諭 | 1978年4月~ 1979年3月(1年) |
|
| 学校法人中京女子大学 中京女子大学附属幼稚園(2010年4月より至学館大学附属幼稚園と改名)教諭・2007年より教務主任 | 1979年4月~ 2013年3月(34年) |
|
| 中京女子大学家政学部児童学科 非常勤講師 | 1995年~ 1997年(後期3年) |
|
| 名古屋学芸大学ヒューマンケア学部 子どもケア学科 講師 |
2013年4月~ 2017年3月 |
|
| 桜花学園大学保育学部非常勤講師 | 2013年10月~ 2017年3月 |
|
| 名古屋学芸大学ヒューマンケア学部 子どもケア学科 准教授 |
2017年4月~ 2023年3月 |
|
| 名古屋学芸大学ヒューマンケア学部 幼児保育学外実習指導室 室長 |
2019年4月~ 2022年3月 |
|
| 名古屋学芸大学ヒューマンケア学部 教職センター(幼・保)実習チーフ |
2022年4月~ 現在に至る |
|
| 名古屋学芸大学ヒューマンケア学部 子どもケア学科 教授 |
2023年4月~ 現在に至る |
受賞学術賞
| 受賞事項 | 年月 | 備考 |
|---|---|---|
愛知県私立幼稚園連盟創立50周年記念 愛知県知事表彰 |
1999年11月 | 愛知県知事 |
主な担当科目と授業の改善と工夫
| 【担当科目名(対象学部・学科)】 |
|---|
教育実習・保育実習における事前事後指導(ヒューマンケア学部 子どもケア学科) |
| 【授業の改善と工夫】 |
|---|
| 保育理論と連動して保育現場の実例及び諸問題の映像や資料を基に、問題解決学習及びディスカッションを取り入れ、学生が対話を通して学びを深化させるように取り組んでいる。また、教育実習指導の授業において、複数教員で幼児教育・保育現場で応用ができる日本の伝統的な音楽としての和太鼓演奏の基本的な指導を行い、学生に対してはアクティブラーニングとしての学びにつながるように取り組んだ。 「子育ての原理」の授業では、学生の授業アンケートの回答のなかで、自主学習の不足を感じたため、 学生が授業内容に関連した調査を行いグループで検討・発表する時間及びレポート課題を設けた。ゼミナールの授業ではアクティブラーニングとして、新城市の野外教育施設の体験的学習を行っている。 |