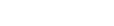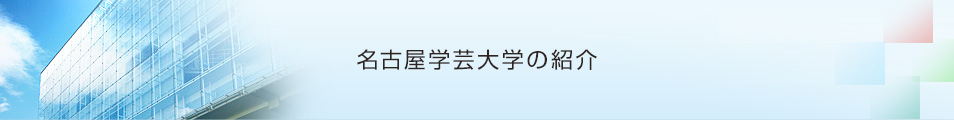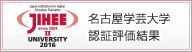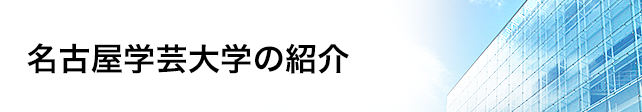
教員組織
教員の教育・研究活動報告
| 所属と職名 | ヒューマンケア学部子どもケア学科幼児保育専攻 准教授 |
|---|---|
| ふりがな | かとう のぞみ |
| 教員氏名 | 加藤 望 |
| 英語表記 | Nozomi Kato |
| 学歴 | 愛知教育大学 教育学部 幼児教育科 |
| 愛知教育大学大学院 博士前期課程 教育学研究科 学校教育専攻 幼児教育領域 | |
| 広島大学大学院 教育学研究科 教育学習科学専攻 博士課程後期 | |
| 学位 | 学士(教育)[愛知教育大学] |
| 修士(教育学)[愛知教育大学大学院] | |
| 博士(教育学)[広島大学大学院] | |
| 現在の研究分野 (最大5つまで) |
こども学 |
| 現在の研究テーマ |
|
主な研究業績
| 【著書】 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 題名 | 単・共 の別 |
発行日 | 発行所名 | 備考 |
| 絵本から「子ども福祉」を考える | 共 | 2016年7月 | 春風社 | |
| 小児リハビリテーションVol.8 | 共 | 2020年12月 | 株式会社ともあ | |
| 保育・幼児教育・子ども家庭福祉辞典 | 共 | 2021年6月 | ミネルヴァ書房 | |
| TEAと質的探究用語集 | 共 | 2025年3月 | 誠信書房 | |
| 【学術論文】 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 題名 | 単・共 の別 |
発行又は発表日 | 発行雑誌又は発 行学会等の名称 |
備考 |
| 幼児と保育者の相互受容関係について | 単 | 2015年3月 | 愛知淑徳大学論集 福祉貢献学部篇 |
|
| 日本の乳幼児教育・保育における持続可能な開発のための教育 ( ESD ) の現状と課題 | 単 | 2016年3月 | 愛知淑徳大学論集 福祉貢献学部篇 |
|
| 幼児期の持続可能な開発のための教育の国際的動向 | 共 | 2016年3月 | 愛知淑徳大学論集 福祉貢献学部篇 |
|
| 父親の自己受容に関する研究:2000年代初頭を対象として | 単 | 2017年3月 | 愛知淑徳大学論集 福祉貢献学部篇 |
|
| 地域型保育事業の実情と課題―事業所内保育事業における実践研究 | 共 | 2017年3月 | 愛知淑徳大学論集 福祉貢献学部篇 |
|
| 保育者養成校におけるアクティブ・ラーニング活用の実態と課題に関する研究―全国保育士養成協議会研究発表論文集を対象として― | 共 | 2017年7月 | 名古屋市立大学大学院人間文化研究科『人間文化研究』 | |
| 子ども主体の考え方に基づく環境構成指導の試み―壁面構成作成に関する学生指導の実践的研究― | 単 | 2018年3月 | 愛知淑徳大学論集 福祉貢献学部篇 |
|
| なぜ日本の乳幼児子育て期の保護者はリフレッシュ目的で一時預かり事業を利用しにくいのか? | 共 | 2018年9月 | 広島大学大学院教育学研究科紀要第三部(教育人間科学関連領域) | |
| マンガに描かれる保育者イメージに関する研究 | 共 | 2019年8月 | 瀬木学園紀要 | |
| 子どもの情緒を安定に導く一時預かり事業担当保育者の実践的知識~リー・ショーマンの「知識基礎」カテゴリーに着目して~ | 単 | 2019年9月 | 国際幼児教育学研究 | 査読有 |
| 高学歴女性の仕事と育児や家事の鼎立を阻む社会的状況―うえの式質的分析法を用いて― | 共 | 2019年10月 | 幼年教育研究年報 | |
| 質的データ分析法としてのSCATとうえの式質的分析法の比較―幼稚園長のインタビューデータから― | 共 | 2019年12月 | 広島大学大学院教育学研究科紀要第三部(教育人間科学関連領域) | |
| 一時預かり事業に生起する葛藤とその背景 | 単 | 2019年12月 | 保育学研究 | 査読有 |
| 女性・母親に向けられるアンコンシャス・バイアスという眼差し | 共 | 2019年12月 | 広島大学大学院教育学研究科紀要第三部 | |
| 学生時代に幼児教育を学ぶことのなかった私立幼稚園園長が子ども主体の保育を実施するに至った背景―うえの式質的分析法を用いて | 共 | 2020年9月 | 国際幼児教育学研究 | 査読有 |
| 海外の保育・幼児教育分野におけるショーマンのPCK概念をめぐる研究動向 ―日本の保育者研究への援用可能性の検討― |
共 | 2020年11月 | 幼年教育研究年報 | |
| 研究方法論としての多声的ビジュアル・エスノグラフィーの可能性と課題 | 共 | 2020年12月 | 広島大学大学院人間社会学研究科紀要「教育学研究」 | |
| 一時預かり担当保育者はどのように子どもの情緒を安定に導くのか? ――「抱っこ」の判断を巡る専門性に着目して |
単 | 2021年3月 | 質的心理学研究 | 査読有 |
| 一時預かり事業の保育者に特有の実践知 ―クラス担当保育者の語りとのずれに着目して |
単 | 2023年2月 | 乳幼児教育学研究 | 査読有 |
| 学外実習先と保育者養成校が協働する実習指導の在り方に関する研究 | 共 | 2023年5月 | 保育者養成教育学研究 | 査読有 |
| なぜB氏は特別支援学校教員として定年退職まで働き続けることができたのか : 複線径路等至性モデリング(TEM)による分析 | 共 | 2023年12月 | 広島大学大学院人間社会科学研究科紀要 | |
| 「hana-TEM:アートで描くわたしの径路」:TEAと質的探究学会第2回大会・研究交流委員会企画ワークショップ | 共 | 2024年3月 | 立命館大学ものづくり質的研究センター紀要『質的研究と社会実装』 | 査読有 |
| 保育者の実践知を探る質的データ分析法としてのSCAT | 共 | 2024年12月 | 広島大学大学院人間社会科学研究科紀要「教育学研究」第5号,pp.148-156 | |
| 【学会発表等】 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 題名 | 単・共 の別 |
発行又は発表日 | 発行学会等の 名称 |
備考 |
| 2歳児の対人葛藤場面における他者受容に関する研究 | 単 | 2016年5月 | 日本保育学会第69回大会 | |
| 保育者養成校におけるアクティブ・ラーニング活用の実態と課題に関する研究 | 共 | 2016年8月 | 全国保育士養成協議会第55回研究大会 | |
| マンガにみる保育者の専門性に関する研究 | 共 | 2017年7月 | 日本子ども社会学会第24回 | |
| The Professionalism of male ECEC teachers in Japanese Manga Culture - A Pilot Study Using Qualitative Visual Content Analysis- | 共 | 2017年7月 | 18th International Conference of the Pacific Early Childhood Education Research Association | |
| 一時預かり保育において保育者は子どもの受容にどんな困難や葛藤を抱えているのか | 単 | 2018年5月 | 日本保育学会第71回大会 | |
| 一時預かり保育における保育者の職務満足感に関する研究 | 単 | 2018年7月 | 中部教育学会第67回大会 | |
| A Study on the Image of Child Care Workers in Manga | 共 | 2018年7月 | 19th International Conference of the Pacific Early Childhood Education Research Association | |
| A Study on the Contents and Management Approaches to System of Temporary Childcare in Japan | 単 | 2018年8月 | European Early Childhood Education Research Association 28th Conference | |
| なぜリフレッシュ目的での一時預かり事業は利用しにくいのか? | 共 | 2018年12月 | 日本乳幼児教育学会第28回大会 | |
| 保育実習日誌から読み解く養成校学生の学びのプロセス | 共 | 2019年3月 | 日本保育者養成学会第3回研究大会 | |
| 女性・母親に向けられるアンコンシャス・バイアスという眼差し | 共 | 2019年3月 | 日本発達心理学会第30回大会 | |
| 通常の保育から一時預かり担当になった保育者はどんな葛藤を抱えているのか | 単 | 2019年5月 | 日本保育学会第72回大会 | |
| 子どもの情緒を安定に導く一時預かり担当保育者の実践的知識~リー・ショーマンの「知識基礎」カテゴリーに着目して~ | 単 | 2019年6月 | 日本子ども社会学会第26回大会 | |
| A Study of Teacher’s Practical Knowledge of Guiding Children’s Emotional Well-being | 単 | 2019年7月 | 20th International Conference of the Pacific Early Childhood Education Research Association | |
| 高学歴女性の仕事と育児や家事の鼎立を阻む社会的状況―うえの式質的分析法を用いて― | 共 | 2019年9月 | 日本質的心理学会第16回大会 | |
| 質的データ分析法としての「SCAT」と「うえの式質的分析法」の比較:幼稚園長のインタビューから | 共 | 2019年9月 | 日本質的心理学会第16回大会 | |
| ライフイベントの「入り口」に向けられるジェンダーをめぐるアンコンシャス・バイアス | 共 | 2020年3月 | 日本発達心理学会第31回大会 | |
| 一時預かり担当保育者はどのように子どもを情緒安定に導くのか?~「抱っこ」をめぐる実践的知識~ | 単 | 2020年5月 | 日本保育学会第73回大会 | |
| 子どもの情緒を安定に導く 一時預かり担当保育者の暗黙知とは何か? |
単 | 2020年11月 | 日本乳幼児教育学会第第30回大会 | |
| 一時預かり事業で生じるノンルーティン保育 ~保育場面映像の微視的分析~ |
単 | 2021年5月 | 日本保育学会第74回大会 | |
| 育児や家事と仕事の鼎立を可能にする社会的支援に関する研究 | 単 | 2021年6月 | 日本子ども社会学会第27回大会 | |
| How Do Early Childhood Teachers in the U.S. View the Class Competition by Five-Years-Old at a Japanese Sports Day? | 共 | 2021年9月 | 国際幼児教育学会第42回大会 | |
| 学外実習先と保育者養成校が協働する実習指導の在り方に関する研究 ~実習生の実習への取り組みに着目して~ |
共 | 2022年3月 | 第6回日本保育者養成教育学会研究大会 | |
| 一時預かり事業の保育者に特有の実践知 ~クラス担当保育者の語りとのずれに着目して |
単 | 2022年5月 | 日本保育学会第75回大会 | |
| なぜ保育者は運動会のクラス対抗競技で子どもたちを競争させるのか︖ ―ある幼稚園の事例から― |
共 | 2022年8月 | 日本教育学会第81回大会 | |
| 米国の保育者は日本の幼稚園における当番活動をどのように捉えるのか? | 共 | 2022年10月 | 日本質的心理学会第19回大会 | |
| Why do the Japanese Early Childhood Teachers Give Young Children Compete in the “Sports Day”?: Focusing on the Case of Class Competition | 共 | 2023年1月 | the Twenty First Annual Hawaii International Conference on Education | |
| ジェンダー・アンコンシャス・バイアスを捉えるための研究方法論的視点を探る ビジュアルからアプローチする試み |
共 | 2023年3月 | 日本発達心理学会第 34回大会 | |
| 映像とオンライン会議システムを活用した保育施設見学の可能性と課題 -実習記録の書き方指導に着目して | 共 | 2023年3月 | 日本保育者養成教育学会第7回大会 | |
| 子育て中の保護者は一時預かり事業をどのように利用しているのか? | 共 | 2023年5月 | 日本保育学会第76回大会 | |
| なぜ日本の保育者はクラスのすべての子どもが当番活動を担うことに肯定的なのか? | 共 | 2023年6月 | 日本子ども社会学会第29回大会 | |
| 子どもの権利を保障する保育を考える | 共 | 2023年6月 | 日本子ども社会学会第29回大会 | |
| 日本の保育者は「背中の保育」をどう捉えるのか?-乳児に対して保育者が背中を用いるアプローチをめぐる語りから- | 共 | 2023年8月 | 日本教育学会第82回大会 | |
| オートエスノグラフィーを用いた博士論文の作成と指導に関する対話的エスノグラフィー | 共 | 2023年11月 | 日本質的心理学会第20回大会 | |
| 保育者の実践知を探る質的データ分析法としてのSCAT | 共 | 2023年12月 | 日本乳幼児教育学会第33回大会 | |
| すべての子どもに平等かつ順番に当番活動を課す日本の保育者の葛藤 | 共 | 2024年6月 | 日本子ども社会学会第30回大会 | |
| How Is the Japanese Forest Kindergarten Understood by Foreign Pre-School Teachers Who Emphasize Outdoor Education? | 共 | 2024年8月 | PECERA Annual Conference 2024 | |
| 「背中の保育」の実践は日本の保育者にどう捉えられるのか?―乳児に対して保育士が背中を用いるアプローチをめぐる語りから― | 共 | 2024年8月 | 日本教育学会第83回大会 | |
| Why Does the Japanese Nursery Teacher Approach Infants and Toddlers Using Her/His Own Back? | 共 | 2024年9月 | 国際幼児教育学会第45回大会 | |
| なぜ日本の保育者はすべての子どもに「当番活動」を課すのか? | 共 | 2024年10月 | 日本質的心理学会第21回大会 | |
| hana-TEM: Exploring Life Trajectories Beyond Verbalization: Expansion of Trajectory Equifinality Modeling and Development of a New Method Using Natural Objects | 共 | 2024年10月 | 第6回TEA国際集会 | |
| Rethinking the Image of the Child and DAP in Peer Relationships: Onsights from a Visual Ethnography of Children Collaborating to Pursue Their Own Goals | 共 | 2024年11月 | NAEYC Annual Conference 2024 | |
| Why Do the Japanese Nursery Teachers Approaching Infants and Toddlers Using Their Own Back? | 共 | 2025年1月 | Hawaii International Conference on Education 23rd Annual Conference | |
| Power of Play:Revisit the Role of Play in Japanese Children’s Learning Using Critical Lens | 共 | 2025年1月 | Hawaii International Conference on Education 23rd Annual Conference | |
主な教育上の業績
| 【大学教育の改善に関する活動】 | |||
|---|---|---|---|
| 活動事項 | 単・共の別 | 年月 | 備考 |
保育実習記録簿の指導計画案書式の追加 |
単 |
2024年8月 |
|
| 保育実習の手引き 加筆修正 | 共 | 2024年8月 | |
幼児保育専攻主催講演会の実施 |
共 |
2024年11月 |
|
| 【作成した教科書】 | |||
|---|---|---|---|
| 教科書名(対象講義名) | 単・共 の別 |
年月 | 備考 |
| 新・保育実践を支える保育の原理(保育原理) | 共 | 2018年2月 | 福村出版 |
| コンパス保育内容「言葉」第2版(言葉) | 共 | 2018年3月 | 建帛社 |
| 子どもの主体性を育む保育内容総論 (保育内容総論) |
共 | 2018年11月 | 株式会社みらい |
| コンパス教育原理 (教育原理) |
共 | 2021年5月 | 建帛社 |
| 児童文化がひらく豊かな保育実践 (児童文化) |
共 | 2022年5月 | 教育情報出版 |
| 【資格・免許】 | |||
|---|---|---|---|
| 資格・免許の名称 | 取得年月 | 発行者・登録番号 | 備考 |
| 保育士資格 | 2002年9月 | 愛知県-020950 | |
| 幼稚園教諭一種免許 | 2003年3月 | 愛知県教育委員会・平14幼一第291号 | |
| 幼稚園教諭専修免許 | 2005年3月 | 愛知県教育委員会・平16幼専第0004号 | |
| 実習指導者認定 | 2023年4月 | 全国保育士養成協議会・220250136 | |
主な職務上の業績
| 【社会的活動等】 | |||
|---|---|---|---|
| 活動事項 | 期間(年月) | 活動機関 | 備考 |
| 中堅後期保育士研修 講師 | 2015年6月~2018年3月 | 尾張旭市 | |
| 公開保育研修 講師 | 現在に至る | 碧南市 | |
| 教員研修 講師 | 2018年4月~2020年3月 | 名古屋私立幼稚園協会 | |
| 公開講座 講師 | 2019年11月 | 愛知みずほ短期大学 | |
| 潜在保育者復職支援プログラム | 2021年6月~2022年3月 | 愛知みずほ短期大学 | |
| シンポジスト | 2024年12月 | 全国保育士養成協議会中部ブロックセミナー | |
| 司会 | 2025年1月 | 中部地区幼児教育研究会 | |
所属学会
| 【所属学会名称】 | |
|---|---|
| 学会名称 | 日本保育学会,日本乳幼児教育学会,国際幼児教育学会,日本子ども社会学会,日本質的心理学会,日本保育者養成教育学会,日本教育学会、TEAと質的探究学会 |
| 【所属学会役員歴等】 | ||
|---|---|---|
| 学会及び役員名 | 年月期間(年月) | 備考 |
| 日本保育学会第68回大会実行委員 | 2015年5月 | |
| 日本子ども社会学会事務局長補佐・広報委員 | 2019年7月~2021年6月 | |
| 国際幼児教育学会第42回大会実行委員 | 2021年4月~2021年12月 | |
| TEAと質的探究学会交流委員 | 2022年4月~2025年5月 | |
| 日本乳幼児教育学会第33回大会実行委員 | 2023年5月~12月 | |
| 国際幼児教育学会第44回大会実行委員 | 2023年12月~現在に至る | |
| 全国保育士養成協議会中部ブロックセミナー実行委員 | 2024年2月~現在に至る | |
| 日本質的心理学会査読協力委員 | 2024年4月~現在に至る | |
| 日本乳幼児教育学会理事 | 2024年11月~ 現在に至る | |
| 日本保育学会編集常任委員会専門委員 | 2025年2月~現在に至る | |
| 国際幼児教育学会理事 | 2025年6月~現在に至る | |
主な職歴
| 事項 | 期間(年月) | 備考 |
|---|---|---|
| 愛知淑徳大学福祉貢献学部 助教 | 2014年4月~2018年3月 | |
| 愛知みずほ短期大学現代幼児教育学科 助教/准教授 | 2018年4月~2022年3月 | |
| 名古屋学芸大学ヒューマンケア学部 准教授 | 2022年4月~現在に至る |
受賞学術賞
| 受賞事項 | 年月期間(年月) | 備考 |
|---|---|---|
| 日本乳幼児教育学会 学術賞 | 2023年12月 | |
| 生活科学系コンソーシアム 学術奨励賞 | 2024年3月 |
科学研究費等外部資金導入実績
| 名称 | 題名 | 年月 | 機関名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 全国保育士養成協議会中部ブロック研究助成 | 保育者養成校におけるアクティブ・ラーニング活用の実態と課題に関する研究 | 2017年6月~2018年3月 | 全国保育士養成協議会 | |
| 日本学術振興会科学研究費助成金若手B(代表) | 一時預かり保育担当保育者の実践的知識に関する研究 (課題番号18K13130) |
2018年4月~2022年3月 | 日本学術振興会 | |
| 全国保育士養成協議会中部ブロック研究助成 | 保育実習日誌から読み解く養成校学生の学びのプロセス | 2018年6月~2019年3月 | 全国保育士養成協議会 | |
| 奨励研究基金 | 育児や家事と仕事の鼎立を可能にする社会的支援に関する研究 | 2020年7月~2021年3月 | 日本子ども社会学会 | |
| 日本学術振興会科学研究費助成金基盤B(分担) | 日米中の保育者の多様な声に基づく「文化的営みとしての保育」概念の構築 (課題番号21H00842) |
2021年4月~現在に至る | 日本学術振興会 | |
| 全国保育士養成協議会中部ブロック研究助成 | 学外実習先と保育者養成校が協働する実習指導の在り方に関する研究 ~学生による学外実習の授業評価に着目して~ |
2021年6月~2022年3月 | 全国保育士養成協議会 | |
| 日本学術振興会科学研究費助成金基盤C(代表) | 一時預かり事業担当保育者の専門性向上に資するオンライン研修プラットフォームの構築 (課題番号22K02426) |
2022年4月~現在に至る | 日本学術振興会 |
主な担当科目と授業の改善と工夫
| 【担当科目名(対象学部・学科)】 |
|---|
子育ての原理 子育て支援論 保育内容総論 ゼミナールⅠ ゼミナールⅡ ゼミナールⅢ 保育実習Ⅰ 保育実習指導Ⅰ(ヒューマンケア学部・子どもケア学科)子育て支援特論(大学院) |
| 【授業の改善と工夫】 |
|---|
| 授業の改善のために、授業実施アンケートだけでなく、学生からの要望や質問を聞く時間を授業後に設けている。授業内で取り扱うデータは、常に最新のものとなるよう、毎年、スライドを更新している。授業で取り扱う内容に関する情報は、書籍だけでなく学会や各種勉強会、研修会を通して更新している。 授業の工夫として、履修者の多い講義科目においても、学生それぞれが安心して自分の意見を述べられるよう、近隣席の学生同士で話し合う時間を取ったり、ICTを利用したりするなどして、意見交換の機会を保障している。また、演習の授業においては、学生が調べ学習を行った成果物を実際にパンフレットとして印刷及び配布することにより、社会貢献に繋がる喜びを感じられるようにしている。 |