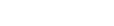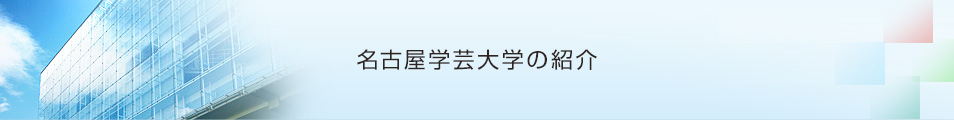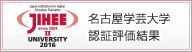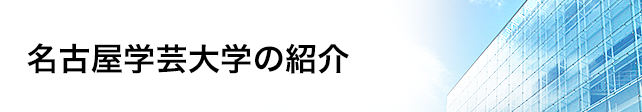
教員組織
教員の教育・研究活動報告
| 所属と職名 | ヒューマンケア学部 教職課程 特任教授 |
|---|---|
| ふりがな | よしむら ただし |
| 教員氏名 | 吉村 匡 |
| 英語表記 | Tadashi Yoshimura |
| 生年 | 1957年 |
| 学歴 | 三重大学教育学部 (4年) 、愛知教育大学大学院(2年) |
| 学位 | 学士(教育)[三重大学] |
| 修士(教育)[愛知教育大学] | |
| 現在の研究分野 (最大5つまで) |
特別支援教育 |
| 現在の研究テーマ |
|
主な研究業績
| 【著書】 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 題名 | 単・共 の別 |
発行日 | 発行所名 | 備考 |
| 「未来へつなぐキャリア教育」 | 共 | 2016年1月15日 | ジアース教育新社 | |
| 【学術論文】 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 題名 | 単・共 の別 |
発行又は発表日 | 発行雑誌又は発 行学会等の名称 |
備考 |
| 「高等学校における特別支援教育の現状と課題~愛知県の公立高等学校教職員へのアンケート調査の結果より~」 | 共 | 2020年3月10日 | 障害者教育・福祉学研究第16巻 | 査読無 |
| 特別支援教育が拓くこれからの教育の可能性-「学生の意識調査」を例に- | 共 | 2022年3月25日 | 名古屋学芸大学ヒューマンケア学部・教職課程研究会 | 査読無 |
| ディスレクシア生徒に提供する合理的配慮に対する高等学校教員の負担感とそれに関連する個人要因について | 共 | 2024年2月25日 | 「LD研究」第33巻第1号 | 査読有 |
| 【学会発表等】 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 題名 | 単・共 の別 |
発表日 | 発行学会等の 名称 |
備考 |
| 学生支援者の養成を目指した授業の開設について | 共 | 2023年9月7日 | 全国高等教育障害学生支援協議会AHEAD JAPAN | |
主な職務上の業績
| 【資格・免許】 | |||
|---|---|---|---|
| 資格・免許の名称 | 取得年月 | 発行者・登録番号 | 備考 |
| 小学校教諭1種免許 | 1981年3月 | 三重県教育委員会 昭五五小一普第三五二号 |
|
| 養護学校教諭1種免許 | 1981年3月 | 三重県教育委員会 昭五五養学一普第四六号 |
|
| 特別支援学校専修免許(知・肢・病) | 2020年5月 | 愛知県気養育委員会 令二特専第一号 |
|
| 【社会的活動等】 | |||
|---|---|---|---|
| 活動事項 | 期間(年月) | 活動機関 | 備考 |
| 愛知県キャリア教育・就労支援推進委員会委員長 | 2021年4月~ 2024年3月 |
愛知県教育委員会 | |
| 障害者雇用審議会・委員長 | 2022年4月~ 現在に至る |
愛知県労働局 | |
| 教育振興事業委員会・委員長 | 2022年4月~ 現在に至る |
公益財団法人日本教育公務員弘済会愛知支部 | |
| 第3期愛知県特別支援教育推進計画検討会議・副座長 | 2023年4月~ 2024年3月 |
愛知県教育委員会 | |
| こどもICTマイスター 応援プロジェクト | 2023年6月 | 愛知教育大学相羽研究室名古屋ディスレクシア協会 | |
| 愛知県労働局指定管理者等選定会議委員 | 2025年6月~ 現在に至る | 愛知県労働局 | |
所属学会
| 【所属学会名称】 | |
|---|---|
| 学会名称 | 日本特殊教育学会、日本LD学会、日本発達障害学会 |
主な職歴
| 事項 | 期間(年月) | 備考 |
|---|---|---|
| 愛知県立佐織養護学校・港養護学校(教諭) | 1981年4月~2003年3月 | |
| 愛知県立一宮東養護学校小学部主事 | 2003年4月~2005年3月 | |
| 愛知県総合教育センター相談部特別支 援教育相談研究室(研究指導主事・室長) |
2005年4月~2008年3月 | |
| 豊田市立豊田養護学校・教頭 | 2008年4月~2011年3月 | |
| 愛知県総合教育センター相談部長 | 2011年4月~2013年3月 | |
| 愛知県立岡崎特別支援学校校長 | 2013年4月~2018年3月 |
主な担当科目と授業の改善と工夫
| 【担当科目名(対象学部・学科)】 |
|---|
| 特別支援基礎概論(ヒューマンケア学部・子どもケア学科、管理栄養学部・管理栄養学科)、教職入門(ヒューマンケア学部・子どもケア学科)、肢体不自由者教育方法論(ヒューマンケア学部・児童発達教育専攻)、教育実習指導(特別支援)(ヒューマンケア学部・児童発達教育専攻)、特別支援教育特論・演習(大学院子どもケア研究科) |
| 【授業の改善と工夫】 |
|---|
| 講義資料はプレゼンテーションソフトで作成し、視覚的にも理解しやすいユニバーサルデザインに留意している。また、映画等のDVDや録画したテレビ番組の視聴を含め、ICT機器を有効活用している。Excelファイルで個別に講義ノートを作成し学生の感想や質問に対応している。寄せられた質問で共通の話題として提供できるものは、その都度全体にフィードバックしている。 最新の知見を精査し、講義に反映できるように努めている。講義で使用した資料のほとんどをPDFにしてMoodleで閲覧できるようにしている。障害のある学生への配慮として、動画には字幕を付けている。また、遠隔講義を実施する際も、動画に字幕を付けるようにしている。大学院では現場の実情に触れるため学校訪問研修を実施し喫緊の課題に触れたのち改善策について具体的に検討する機会を設けている。 |